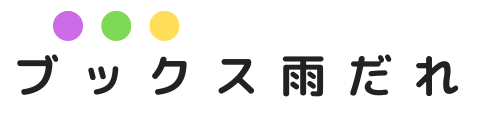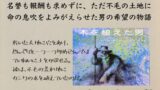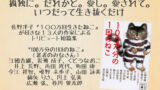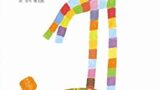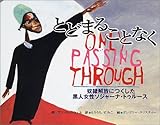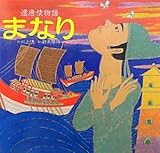みなさんの本との出会いの原点はどこですか?おうちの人に、保育園や幼稚園の先生に読み聞かせてもらったお気に入りの絵本はなんでしたか。
ページをめくると広がる物語の世界。みなさんの中にも、幼いころの大切な絵本との懐かしい記憶があるのではないでしょうか。
絵本は小さなこどものためのもの、というわけではありません。
10代の少年少女にこそ感じて欲しい絵本があります。小さなページに込められた強いメッセージは、きっとあなたの心に響くはず。いくつになっても大切にしたいような、何度でも読み返したくなる、そんなおすすめの絵本を紹介します。
- のんびりと肩の力を抜いてページをめくる。
- お茶など飲みながら読むのがベスト。
- 英語で味わう原書版もおすすめ。
- 10代へのよみきかせや贈り物にもぴったり。
※こちらのページは随時加筆されています。
物語を味わう絵本
1.『ぜつぼうの濁点』
原田 宗典 (著), 柚木 沙弥郎 (イラスト)
昔むかしあるところに言葉の世界がありましてその真ん中におだやかなひらがなの国がありました。ひらがなの国でおきたふしぎなお話です。
登場するのはひらがなばかりという絵本。「ぜつぼう」の「〃」だった濁点は、自分がいるから不幸なのだと「ぜつぼう」のもとを離れますが、だれも引き取り手がありません。みんなに「いやな奴」扱いをされてしまう「〃」の切なさと、視点を変えるだけで希望が生まれるおもしろさが味わえます。
2.『二番目の悪者』
金のたてがみをもつライオンは、自分は特別な存在だと信じていた。自分こそが次の王さまにふさわしいと考えた金のライオンは、ある作戦をおもいつく・・・。わたしたちの身の回りで実際にありそうなこの物語。悪いのはこの人だ、と言い切れるだろうか。考えさせられます。
3.『木を植えた男』
1987年アカデミー賞短編映画賞受賞。戦争で荒れてしまった土地に森をとりもどすために、たったひとりでどんぐりの苗を植え続ける男の物語。彼が言葉にしないメッセージを受け取って欲しい。
4.『アンジュール』
白い画用紙に茶色のクロッキーで描かれたある一匹の犬の物語。文章はありません。絵だけで語られる、犬の切ない痛み、悲しみ、置きどころのない心があふれ出てくるような絵本です。絵を描く人には、デッサンの勉強にもなるかもしれませんね。
5.『ビロードのうさぎ』
男の子と大好きなうさぎのぬいぐるみの物語。わたしたちは成長するにつれて、なにかを手に入れ何かを失っていく。失ったことに気が付くのは、ずっとあとになって振り返った時なのでしょう。それを切なさと呼ぶのかもしれません。酒井駒子さんの絵が美しく、ずっと手元に置いておきたい絵本のひとつです。
6.『100万回生きたねこ』
何度も死んでは生き返ったねこ。ねこはいくつも飼い主たちとの別れを経験してきたが、悲しむことはなかった。ただ生まれ、ただ死んでいく。しかし、ある時ねこは誰のねこでもなかった。そして、ねこは初めての恋をする。一度しかない人生、自分の人生を生きよう! この絵本が好きな人は、オマージュアンソロジー『100万分の一回のねこ』も合わせてどうぞ。
7.『ルピナスさん―小さなおばあさんのお話』
ルピナスさんは、海をみおろすおかのうえにある、小さないえにすんでいます。いえのまわりには、あおや、むらさきや、ピンクの花が、さきみだれています。ルピナスさんは小さなおばあさんですが、むかしからおばあさんだったわけではありません。世界中を旅行しましたし、「世の中を美しくする」ためにステキなことを思いつきました。
ルピナスさんが幼いころおじいさんから言われたことば「世界を美しくする」ことは、社会のためにできる生きがいを見つけること、だと思うのです。人生は楽しいだけでは足りない。だれかを喜ばせるような次の世代に自分はなにを残せるだろうか、そんなことを考えさせられます。高学年からのよみきかせでも、じっくりと聞いてくれました。
8.『百年の家』
国際アンデルセン賞画家賞受賞インノチェンティの傑作
人が家に命を吹き込み、家が家族を見守る。家と人が織りなす100年の歳月。
9.『綱渡りの男』
1974年8月7日、完成間近のニューヨーク・世界貿易センターのツイン・タワーの間を、綱渡りした男がいた!若き大道芸人・フィリップ・プティが地上400メートルの高さで繰り広げるパフォーマンス。いまはなきタワーの思い出として、人々の驚嘆と喜びを描いた迫力ある絵本。2004年コールデコット賞ボストングローブ・ホーンブック賞「絵本部門」受賞。
実話をもとにしたドキュメンタリータッチの絵本です。実際には、お騒がせ事件とも言えるプティの挑戦は、多くの人にドキドキと感動を与えました。超高層タワーのあいだに渡した一本のワイヤーの上を慎重に歩くプティ、かたずを飲んで下から見上げる通行人たちを上空から見下ろす見開きページは、よみきかせでも子どもたちのドキドキが伝わる見どころです。いまはもうない、世界貿易センターについても興味がわいたら調べてみてね。
10.『やくそく』
わたしは、スリだった。じぶんと同じようにまずしい人たちから物をぬすんで、生きていた。ある晩、くらい通りで、ひとりのおばあさんに出会った。カバンをひったくろうとすると、おばあさんが言った。「おまえさんにやるよ。これを植えるってやくそくするんならね」あのとき、おばあさんとかわした「やくそく」。その意味に気づいたとき、少女は、それをまもるためにうごきはじめた。
おばあさんとの約束を守ろうと動き出したわたし。そこから少女の世界が少しづつ色づき始めます。少女の動きに合わせて、ニコラ・デイビスの絵が少しづつ変化していくようすに、ページをめくりながら、心も軽くなっていく爽快感があります。静かに心に響く物語。中学生へのよみきかせでも、じっくりと聞いてくれます。
12.『100年たったら』
ずっと昔、草原にライオンがひとりっきりで住んでいました。ある日、飛べなくなった一羽の鳥が草原におりたち、一緒に過ごすようになりますが……。ライオンと鳥がたどる、はるかな時と巡る命を描いた、せつなく壮大な物語。 永遠を感じさせるような、心に響く物語です。一度読んですっかりとりこになってしまいました。よみきかせや贈り物にもおすすめです。
自分と向き合う絵本
13.『ぼくを探しに』
何かが足りない/それでぼくは楽しくない
足りないかけらを探しに行く/ころがりながらぼくは歌う
「ぼくはかけらを探してる、足りないかけらを探してる、ラッタッタ さあ行くぞ、足りないかけらを……」
歌い、転がりながら、自分に足りないなにかを探しに出かける「ぼく」。線だけで描かれたとてもシンプルなイラストですが、人生に普遍的なたくさんのテーマを含んでいます。視点を変えるといろんな見方ができます。中学生以上には、英語版もいかがですか。贈りものにもおすすめです。
14.『ペツェッティーノーじぶんをみつけたぶぶんひんのはなし』
自分をとるに足りない小さな部分品だと思っていたペツェッティーノ。自分はだれの部分品なのかを確かめるために、友だちを訪ね、とうとう海をわたることに…。レオ=レオニのメッセージがモザイクの技法で描かれています。
自分のことをとるにたらない小さな存在だと落ち込んでしまいそうな人に、ぜひこの本を手にしてほしい。「自分はじぶん」というペツエッティーノのメッセージに勇気づけられます。
15. 『こころの家』
キム ヒギョン (著)
イヴォナ・フミエレフスカ (イラスト)
かみや にじ (翻訳)
目には見えないけれど、だれにでも、こころはある。きみにも、ぼくにも。でも、こころってなんだろう。――こころを家にたとえて語る詩的なことばと、イマジネーション豊かなイラストのコラボレーションが、静かで深い印象を放つ。頁の動きをいかした斬新な表現で、ボローニャ・ラガッツィ賞に輝いたオールエイジ向け絵本。
こころとはなんだろう?だれもが持っているのに、漠然としていてとらえどころがない「こころ」を動きのある絵本で語ります。ゆっくりページをめくってみてください。自分のこころと向き合う瞬間があるかもしれませんよ。
16.『ジェーンとキツネとわたし』
カナダ総督文学賞受賞作。学校でひとりぼっちになってしまったエレーヌは、ひとりになったことで自分の中の「弱い自分」を見つめ「自分」という強さを身に付けていきます。いつも彼女のそばにある『ジェーン・エア』の本と、キャンプで出会ったキツネが彼女に勇気を与えます。表情豊かなエレーヌのイラストと文章がぴったりとマッチした絵本。
人生とは
17.『大きな木』
幼い男の子が成長し、老人になるまで、温かく見守り続ける1本の木。
木は自分の全てを彼に与えてしまいます。それでも木は幸せでした。
無償の愛が心にしみる村上春樹訳の世界的名作絵本。
少年が成長し経験を経て老いてゆく、姿を変えながらずっと見守る1本の木。ただ、誰かのために自分を尽くし、だれかに頼られることの喜びを得る。人と人との深い結びつきについて考えさせられます。
18.『葉っぱのフレディ―いのちの旅』
わたしたちはどこから来て、どこへ行くのだろう。生きるとはどういうことだろう。死とは何だろう。人は生きているかぎりこうした問いを問いつづけます。この絵本が自分の人生を「考える」きっかけになることを祈ります。本書は、アメリカの著名な哲学者レオ・バスカーリア博士が「いのち」について子どもたちに書いた生涯でただ一冊の絵本です。 中学生からは英語絵本もおすすめです。
悲しみと向き合う絵本
19.『かないくん』
20.『悲しい本』
「悲しみがとても大きいときがある。どこもかしこも悲しい。からだじゅうが、悲しい。…息子のエディーのことを考えるときがいちばん悲しい。エディーは死んだ。
私は彼を愛していた。とてもとても深く。でも、彼は死んでしまった。」
21.『くまとやまねこ』
だって、ぼくたちは ずっとずっといっしょなんだ───
突然、最愛の友だち・ことりをなくしてしまった、くま。かなしみのあまり、くまは、くらくしめきった部屋に閉じこもる。
だがくまにも、花咲く時は訪れて…夢のコンビで贈る感動の絵本。
22.『いつもだれかが』
いつもだれかが、そばにいた。あぶないときにはたすけてくれた…。幸運だった一生をふり返る祖父と耳を傾ける孫、二人を「見守る存在」を描き、子どもから大人まで、しみじみと心が癒される作品。ヨーロッパ中で大きな話題を呼び、ドイツで異例の書店店頭での平積みが続いている話題の絵本。
考える感じる絵本
23.『 多毛留〈たける〉 』
漁師の父と朝鮮からやってきた母との間に生まれた多毛留(たける)。違いを受け入れない人々の目はやがて悲しみへと向かいます。見るものを強くとらえる美しく繊細な絵と哀しく胸を打つ物語。日本から一番近い国・朝鮮、ふたつの国のあいだにはるか昔からあるつながりや偏見について考えさせられます。
24.『花さき山』
25.『はせがわくんきらいや』
長谷川くん泣かんときいな。わろうてみいな。もっと太りいな。長谷川くんだいじょうぶか。長谷川くん…。乳児の頃ヒ素ミルクを飲んだ著者が、幼少のときのことを思い出しながら描いた絵本。昭和51年すばる書房初版の復刊。
26.『わたし いややねん』
27.『わたしのいもうと』
28.『からすたろう』
八島 太郎 (著)
29.『泥かぶら』
くすのき しげのり (著)、 伊藤 秀男 (イラスト)、 眞山 美保 (原作)
みにくいから、きたないからと、「泥かぶら」と呼ばれ、ひどい仕打ちを受けている女の子がいました。 強い心をもち、人の身になって生きることを伝えます。
絵本というアート
30.『光の旅 かげの旅』
アン・ジョナス (著), 内海 まお (翻訳)
上下さかさまにすると、まったく違った景色が見えてくる不思議な絵本です。白と黒で描かれた光と影の世界。シンプルでいて大胆。よみきかせでは、毎回子どもたちから「うわぁ」という声があがります。
31.『よあけ』
ポーランド生まれのコールデコット賞画家ユリー・シュルヴィッツの絵本には、ほかにも『ゆき』『あめのひ』など鮮やかな風景を切り取った作品が多く、幼いころに読んだことがあるという人も多いのではないでしょうか。みなさんは「よあけ」を見たことがありますか?この絵本のページをめくる時は、自分の中にいつか見た朝やけの景色が広がります。
32.『漂流物』
砂浜に流れ着いたカメラ。現像した写真に写っていたのは、海の中のちょっと不思議な世界。文字のない絵本は、想像力を掻き立てます。「ありえない」と笑いながらも、「もしかしたら本当にこんな世界があったりして…」と遊び心をくすぐります。『海底二万マイル』のようなロマンを感じる絵本。
33.『ZOOM』
文字がない、絵だけで進んでいくストーリー。ページをめくるたびに絵の中に吸い込まれていくようなワクワクする感覚が味わえます。手に取ってページを開いたら、みんな最後まで読んじゃう1冊。
平和について考える
34.『戦争で死んだ兵士のこと』
今はのどかな森のほとり、ひとりの兵士が死んでいる。彼の人生を少しづつ巻き戻していくと・・・。短い言葉とシンプルなイラストが静かに時間をさかのぼるという、それだけの小さな本に込められた強くシンプルなメッセージ。中学校国語教科書でも紹介されています。
35.『おとなになれなかった弟たちに…』
戦争のさなか、食べるものがなかった時代に生まれてきた小さな弟。母もじゅうぶんな母乳を与えてやることができず、弟は赤ん坊のまま、栄養が足りなくて死んでしまった。少年が抱えていた空腹とみじめさと罪悪感に胸が痛みます。中学校国語の教科書にも掲載されています。
36.『さがしています』
アーサー・ビナード (著), 岡倉 禎志 (写真)
ここに登場するのは、あの日ヒロシマに残された「モノ」たち。あるものは姿を変え、あるものはそのままの形を残したたずんでいます。人々の日常が一瞬で奪われ、もう戻ることはないのだという現実を重く受け止めます。
ほかにも戦争絵本をまとめたブックリストはこちらです。

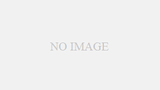
勇気を与える物語
37.『ローザ』
公民権運動の母として、アメリカの歴史の中でもっとも有名な人物のひとりであるローザ・パークス。彼女の静かな決断が、やがて全米を動かす大きな運動を引き起こした。時代を超えて、すべての人々に夢と希望を与えるノンフィクション絵本。2006年度コルデコット賞銀賞、2006年度コレッタ・スコット・キング賞受賞作。
かつてバスの席は白人が前、黒人がうしろと決まっていました。白人と黒人が座れるまんなかの席に座っていたローザに、運転手が「白人に席を譲るよう」に迫ると、ローザはそれを拒絶しました。のちに大きな民権運動に発展したローザの勇気ある行動に、本当の「強さ」を感じます。
38.『とどまることなく 奴隷解放につくした黒人女性ソジャーナ・トゥルース』アン ロックウェル
アメリカの火星探査機にその名をのこす「ソジャーナ」の勇気と力に満ちた半生を描く。1969年全米図書館協会によって設立され、年に一度、きわだってインスピレーション満ち、黒人運動に貢献をした作品、画家、作家に対して授与されるコレッタ・スコット・キング・オナー賞受賞。
歴史・伝記絵本
39.『THE WALL 鉄のカーテンの向こうに育って』
家では、なんでもすきなものをかいたが、学校では、かきなさい、といわれたものをかいた。戦車をかいた。戦争をかいた。教わったことに何の疑問ももたなかった。やがて、教わらないこともあると知った。
1949年チェコスロバキア生まれの絵本作家・ピーター・シスの自伝的絵本です。第二次世界大戦後、共産主義国と社会主義国の冷戦が続き、その緊張状態は「鉄のカーテン」と呼ばれました。閉ざされた支配のもとでいつしか奪われていた自由求めた青年の苦悩と闘いの日々を描きます。2008年コールデコット・オナーブック受賞。
40.『遣唐使物語 まなり』
2004年の秋、中国の西安で工事現場から「墓誌」と言われ石が出土された。そこに彫られていたのは「井真成」という名前と「日本」という国号。これは、命をかえりみず大海を渡った遣唐使と、彼らを支えた人たちの物語。資料の乏しいこの時代を学ぶ貴重な絵本です。
41.『アライバル』
世界各国29の賞を受賞、世界中に衝撃を与えたグラフィック・ノヴェル、ついに刊行! 漫画でもコミックでもない、素晴らしいSF(センスオブワンダー)に満ちた「文字のない本」。
新しい世界への絵本
42.『はじまりの日』ボブ・ディラン
名曲「フォーエバー・ヤング」の絵本。ボブ・ディランの半世紀の道を一緒にたどってみませんか?アメリカ生まれの詩人アーサー・ビナードによる歌える日本語訳。 中学生のよみきかせにも。
43.『IMAGINE イマジン 〈想像〉』ジョン・レノン
あの名曲「イマジン」が絵本に! 1羽の鳩が一生懸命に伝えまわっているもの。それは国を越えた平和と友愛でした。