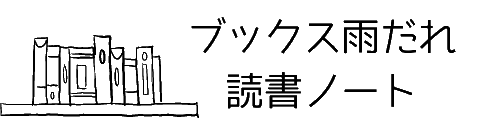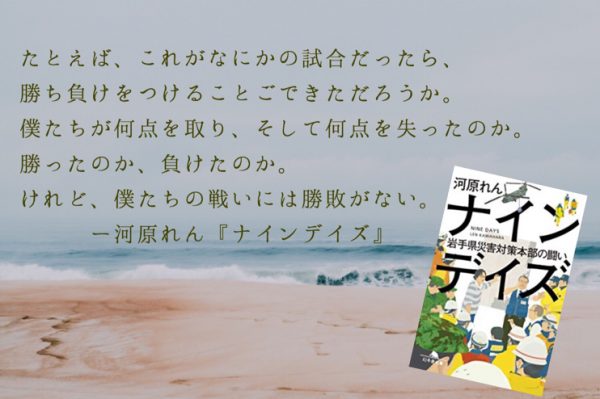2011年3月11日、大きな地震が東北を襲った。だれも経験したことのない恐怖と不安の中、助けを待つ人のもとへと懸命に走った人たちがいる。岩手県災害対策本部、震災発生直後からの怒涛の九日間を実際のできごとをもとにつづった小説。
あらすじ
夢とも、現実ともつかない。
もうすべて投げ出して、ただ力なく笑うしかない。地に足が付いていないふわふわとしたような、あの数日間の感覚がよみがえって、涙をこらえるような思いだけが込み上げる―涙はなぜか出ない。
この本が、フィクションのエンターテエイメント小説だったら、と読みながら何度も思う。
ただ、「設定が面白い」「エキサイティングでした」という感想が言えたらどんなにかいいだろうかと。
こうして活字で読み返してみて、それほどに現実味のないような、想像しえない事態が次々と畳みかけるように起こっていたのだと、改めて愕然とする。
2011年3月11日、忘れるはずもない、あの日は金曜日だった。
頑張っても立っていられないほどの大きな揺れに襲われた。いつまでも収まらない揺れの中、みんなを建物の外に避難させた。津波の知らせは仕事を終えた後、ラジオからだった。
3メートルと言われた津波予想は、すぐに6メートルに変更された。3メートルや6メートルの津波など聞いたことがない。30cmの間違いではないのか、と言った人もいた。津波はほんの30cmでも簡単に足元をさらう威力をもつ。
もう十年も前のことだが、三陸のすぐ海の近くに住んでいたことがある。近所の電信柱にはチリ大地震の時の津波の位置が記されていたし、引っ越してまず最初に家族で津波の際に避難する裏山への道のりを確認した。三陸沿岸には、大きな津波被害の歴史がある。お年寄りから子どもたちまで、防災意識がとても高い。そんな地域でも、防ぎようない大きな災害に襲われた。
岩手県対策本部の九日間
大きな揺れが始まった時、医大の救命医である秋冨は盛岡市の隣町にいた。あの「宮城県沖地震」がついにやってきたか、という怖れを感じていた。怖いのは地震だけじゃない。地震の次に来るものだ。やがてこの地震は、彼が想定したよりもはるかに大きな規模となり「東日本大震災」と呼ばれる。
秋冨はすぐに県庁の総合防災室にコールし、盛岡市内へと道を急いだ。秋冨は救急医として災害医療を研究し、災害派遣医療チーム<DMAT(ディーマット)>で現場経験を重ね、理想論だという人たちを説得し、いつか起こりうる大規模災害のための危機対応システムを岩手県で整えていた。
災害に備えた医療システム、警察や消防、医療との組織連携、整備は整っていたつもりだった。しかし、その地震の規模は想定をはるかに超えていた。止まらない余震、予測のつかない津波の規模、そして電気も電話も情報を伝える手段もすべてのライフラインが止まっていた。
生存者救助に残された時間には限りがある。
ひとりでも助かるはずの命を救いたい。
次々と流れてくる被害状況に動揺して立ち止まる時間もなく、生存者救助に全力を懸けた岩手県災害対策本部の九日間のノンフィクションノベル。
小説だとわかっていても秋冨慎司さん自身の著書かと錯覚するほど、穏やかさの中にも、現場の緊張感ややるせなさ、怒りが、直に伝わる。みんなが必死だったように、県政もできるだけのことをしてくれていたのだとわかる。県民のことを一番に考えてくれる、こんな県に暮らしていることを誇りに思うと共に、その情熱が必ず県の復興を果たしてくれるはずと希望につなげたい。しかし、政府の対応の悪さ・遅さには腹立ちますが。
震災の過酷な状況が甦る。いまは無理でも、いつか復興を遂げたと言える時が来たら、後世にこの震災を伝えるために映像化してほしい。そういう意味でも、ぜひたくさんの人に手に取って読んでほしい1冊です。
本をチェックする
【単行本】
出版社 : 幻冬舎
発売日 : 2012/2/24
単行本 : 254ページ
【文庫本】
出版社 : 幻冬舎
発売日 : 2014/1/29
文庫 : 290ページ